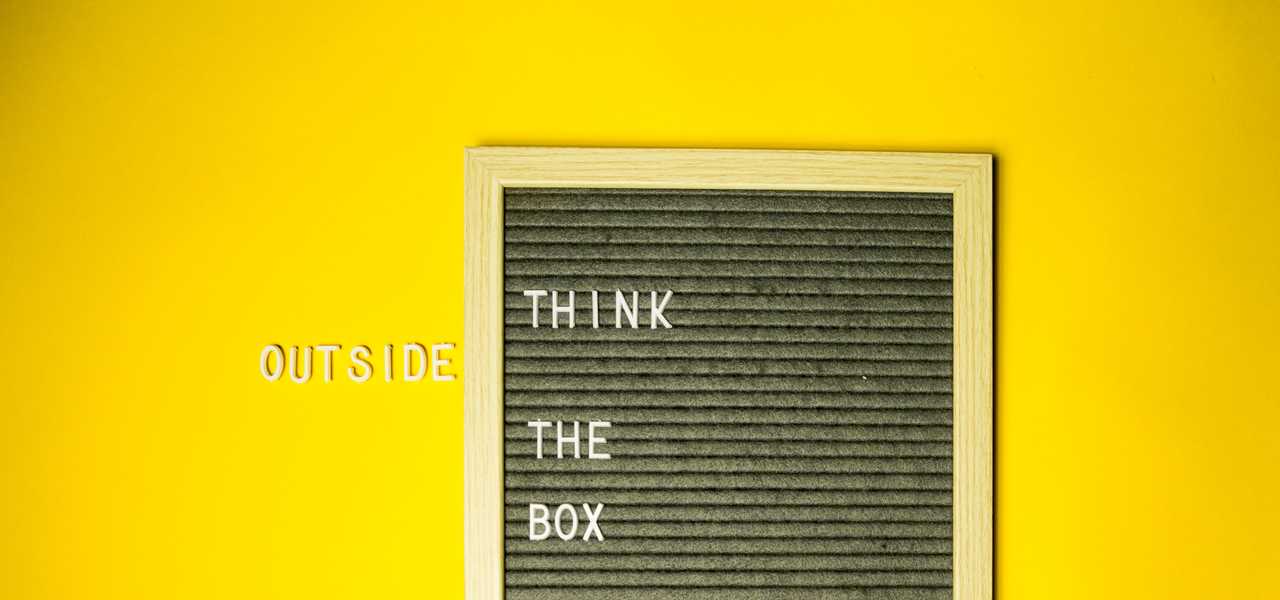あてにならない自分の考え
自分の考えというのは自分が一番分かっていて、正しいと思いがちだ。でも意外とあてにならないし、自分の考えを客観的に見るというのはとても大事だと思う。この3冊の本はSNSで別々に流れてきて面白そうだと思って買った。
- 『脳の外で考える』
- 『Chatter』
- 『確率思考』
買うときは気づかなかったけど、読んでみると人は自分の考えを客観視すべきでそれには方法があるという点で共通していた。
脳の外で考える
脳の外で考える、は個人の理性と理解しがちな、考えるということをいろんな観点で押し広げてくれる。頭の中に押しとどめるのではなく、体の感覚、そして環境、他の人と一緒になど私たちはいろいろな方法で考えることができる。ぼくがやってよかったなと思ったのは、話を聞いたりしたときに体で受け止めるということ。話を理解するだけではなく、受け入れるという意識で話を聞くというのはとてもいいかも、と思っている。難しいけど。あとは、もう少し話をする人の場というのを意識して、話を聞く。
Chatter
また、Chatter、は自分の中で反芻しがちな考えを見直す手がかりを提供している。より長い時間のスパンで考えたり、自分に対してあなたと呼びかけることで客観的になったりすることができる。これは思い出してみると、プログラミングではまってしまったときに人に説明するラバーダックというのはけっこう効果がある。これを他の問題でもやってみるといいかもしれない。あとは、自分を過去とのつながりで捉えるというのは忘れがちだけど、墓参りの時にでもやってみようと思うし、子どもに先祖の話をすると面白いと思う。
確率思考
確率思考では、自分の意見の確かさを50%など確率で表現することで、より自分の意見に対して客観的になれると言っている。また、自分が損をすると思うと真剣になると言った話もあった。そして、いい決断が必ずしもいい結果を導くとは限らないので分けて考える必要があるという話もあった。前職で情報試算のリスクアセスメントの作業をやったことがあるが、数字として目安が出るとちゃんとリスクが分かるように思ったのを思い出した。仕事や転職などをAまたはBで考えるのではなく、論点を立てて確かさを考えるといい判断ができるかもしれない。
盆栽のように客観視する
どの本も自分を客観視するための方法論を提供してくれている。この客観視というのは、とても難しくて、日記をつけると同じ観点になるし、内省は頭のおしゃべり=Chatterになるし、人に話すのははばかられる。一方で、最近は課題に向き合うという表現が良くされる。ただ、この向き合うというのはちょっと危ないように思う。物事に没頭するのは楽しいけど、少し距離を置いて、いろんな角度から眺めると良い案が浮かぶんじゃないかと思う。このサイトもそんな感じで見直しの道具にしたい。
自分のサイト、自分が一番見てる。
— かざいむ@ラオス (@kazaimu_) March 30, 2023
なんか手元にメモしておくより距離が置けていい感じ。盆栽みたいに触りたくなる。
UnsplashのDiana Parkhouseが撮影した写真